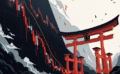【知らないと損】副業収入を賢く増やす!税金の基本から新NISA活用術まで
最近、副業を始める方がとても増えていますよね。でも、「頑張って稼いだお金、税金で思ったより手取りが減ってしまった…」なんて経験はありませんか?あるいは、「少しずつ貯まってきたこのお金、どうやって将来のために活かせばいいんだろう?」と悩んでいませんか?
この記事を読めば、そんなあなたの悩みがスッキリ解決します!副業で得た大切なお金を守る「節税」の基本と、そのお金をさらに育てる「資産形成」の具体的な方法を、専門家と一緒に学んでいきましょう。
ヒロキさん、こんにちは!最近、副業の収入が年間20万円を超えそうなんです。よく「20万円の壁」って聞くけど、これって超えたら何か大変なことになるんですか?
ユイさん、良い質問ですね!多くの方が誤解しているポイントです。「20万円の壁」というのは、正確には「給与以外の所得が年間20万円を超えたら確定申告が必要になる」というルールなんです。逆に言えば、20万円以下なら所得税の確定申告は不要ですが…。
じゃあ、20万円ギリギリに抑えればOKなんですね!よかった〜!
それが落とし穴なんです!実は、所得税の申告が不要でも、住民税の申告は必要なんですよ。申告しないと後で追徴課税される可能性も…。だから、副業収入があるなら金額に関わらず申告する、と覚えておくのが安心です。
手取りを最大化!今すぐできる副業の節税テクニック3選
どうせ申告するなら、しっかり節税して手元に残るお金を最大化したいですよね。ここでは、副業初心者でも始めやすい3つの節税テクニックをご紹介します。
① 経費を漏れなく計上する
副業で収入を得るためにかかった費用は「経費」として計上できます。売上から経費を差し引いた金額が「所得」となり、この所得に対して税金がかかります。つまり、経費をきちんと計上すれば、課税対象の所得を減らせるのです。
経費って、具体的にどんなものが認められるんですか?
例えば、こんなものがありますよ。
・パソコンやスマホの購入費
・打ち合わせのカフェ代や交通費
・スキルアップのための書籍代やセミナー参加費
・仕事で使う文房具やソフトウェア代
プライベートと兼用しているものは、仕事で使った割合分だけを経費にする「家事按分」という考え方も使えます。領収書やレシートは必ず保管しておきましょう!
② 青色申告に挑戦して控除額アップ!
確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。少し手間はかかりますが、「青色申告」を選ぶだけで最大65万円の特別控除が受けられるなど、税制上のメリットが非常に大きいです。
「開業届」と「青色申告承認申請書」を税務署に提出するだけで始められます。最近は便利な会計ソフトも多いので、昔よりずっと簡単に挑戦できますよ。
③ iDeCoやふるさと納税で所得控除を活用
iDeCo(個人型確定拠出年金)やふるさと納税は、支払った金額が所得から控除される「所得控除」の対象です。これらを活用すれば、本業と副業を合わせた所得全体にかかる税金を減らすことができます。
年間で約48,000円もお得に!
iDeCoは将来の年金を作りながら、今の税金を安くできる一石二鳥の制度。副業で得た収入の一部をiDeCoに回すのは、とても賢い選択です。
節税で浮いたお金を「育てる」新NISA活用術
節税は、いわばお金の「守り」のテクニック。ここからは、守って生まれた余裕資金をさらに増やす「攻め」の資産形成について見ていきましょう。副業初心者に最適なのが、2024年から始まった新NISA(少額投資非課税制度)です。
NISAってよく聞きますけど、何がいいんですか?投資ってちょっと怖いイメージもあって…。
良いポイントですね。新NISAの最大のメリットは、投資で得た利益に通常かかる約20%の税金がゼロになることです。しかも、月々1,000円といった少額から始められます。副業で得た収入の一部、例えば月5,000円や1万円からコツコツ積み立てるのがおすすめです。
それなら私にもできそう!何に投資すればいいんでしょうか?
最初は、全世界の株式にまとめて投資できる「全世界株式(オール・カントリー)」や、アメリカの有力企業に投資する「S&P500」といったインデックスファンドがおすすめです。世界経済の成長に合わせて、お金が雪だるま式に増えていく「複利」の効果が期待できますよ。
本日のまとめ
- 副業所得20万円以下でも住民税の申告は必要!
- 節税の基本は「経費計上」「青色申告」「所得控除」の3つ。
- iDeCoやふるさと納税で、今の税金を賢く減らそう。
- 節税で生まれたお金は新NISAで非課税投資。少額からコツコツが成功の秘訣。
副業で得た収入は、あなたの頑張りの結晶です。正しい知識を身につけて、税金で損をすることなく、賢く資産形成につなげていきましょう。まずは、今年かかった経費をリストアップすることから始めてみませんか?小さな一歩が、未来の大きな安心につながりますよ。